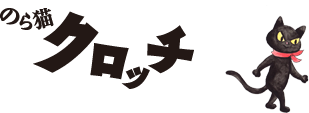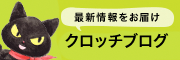クロッチ物語
「似たものどうし」 作:かりにゃん
 「やっぱ、あいつ親方にそっくりっすよ」。金髪を五分刈りにした新入りの軽口に「バカヤロー、猫といっしょにするな」とすごんではみたものの、鳶(とび)の親方はまんざらでもありませんでした。
「やっぱ、あいつ親方にそっくりっすよ」。金髪を五分刈りにした新入りの軽口に「バカヤロー、猫といっしょにするな」とすごんではみたものの、鳶(とび)の親方はまんざらでもありませんでした。
ここんとこ、鼻タレのわるガキもガラのわるいドラ猫も姿を消しちまった。あんなヤツ、久しぶりだぜ……。
それは、とあるビルの改修工事をはじめて間もないころでした。身の丈よりはるかに長い資材を担いで、地上3階の高さの足場を行き来していた親方は、現場の隣にそびえる松の木の上でこちらを見上げる1匹の黒猫に気がついたのです。 黒猫はあくる日もそのあくる日も松の上から親方を見つめているのでした。
うららかな春の陽射しを浴び、大きく伸びをしたクロッチは、ゴロリと寝返りをうちました─「それにしても……オイラより高いところに登れる人間がいたなんて」。
クロッチの自慢は「いつでもどこでもどの猫よりも、一番高い場所に陣取ること」でした。ところが、あの松のてっぺんよりもはるかに高いところを歩いている人間たちがいたのです。中でもクロッチの目をくぎづけにしたのは、目つきの鋭い白髪頭の男でした。小柄でありながら、重そうな荷を担いで幅の狭い足場板の上をひょいひょいと移動する姿を、クロッチは尊敬と称賛のまなざしで追い続けていたのです。
昼になり、弁当を広げた親方は、積み上げた資材の陰からこちらをじっと見ている猫に気がつきました。あの黒猫です。目尻がぐいっと上がったワルそうな目。なんと強烈な目めぢから力でしょうか。「おまえ、なんで毎日オレのこと見てんだよ」─話しかけながら親方は、まだ口をつけていない焼きシャケをそのまま猫の足もとに投げてやったのです。
一瞬、ためらうようなそぶりを見せた後、すっと前に進み出た猫は親方の目の前でゆっくりとシャケをたいらげました。こびるでもない、人を恐れるでもない、堂々とした食べっぷりにいたく感心した親方は、毎日やってくるようになった猫のためにシャケ弁を買ってきては、切り身をそっくりそのままを与えるようになったのです。
 「のら猫」の誇りをもつクロッチは、「なるべく人間から食べ物はもらうまい」と努めていました。
でも、今回は例外中の例外です。なんといっても、自分より高いところに登れる鳶の親方からの「こころざし」なのですから。
「のら猫」の誇りをもつクロッチは、「なるべく人間から食べ物はもらうまい」と努めていました。
でも、今回は例外中の例外です。なんといっても、自分より高いところに登れる鳶の親方からの「こころざし」なのですから。
改修工事もあますところ数日となったその日、「おう、クロ、おそかったな」と、親方は勢いよく焼きシャケを放りました。すると、どこに潜んでいたのか、茶と黒のベッコウ模様の猫が飛び出してきて、シャケに前脚をのばした黒猫に思いきりパンチをくらわせたのです。黒猫は、とっさに身を引き、かろうじて一撃をかわすとすさまじい形相で無作法ものをにらみました。が、突然きびすを返すと、なにごともなかったかのように去っていったのです。あくる日、姿を見せたのはベッコウ猫でした。親方にしてみれば、強引に割り込んできた新参者に、シャケの皮でさえめぐんでやる義理も筋合いもなかったのですが、どういう理由か自ら身を引いた黒猫の気持ちを重んじ、工事が終わるその日まで、ベッコウ猫にシャケを与えることにしたのです。
クロッチからとびきりのごちそうをせしめたのは気性の荒いチャックロというのら猫でした。いつものクロッチであれば、エサを横取りしようとするものなど許しはしなかったでしょう。しかし、パンチをかわしたその瞬間、クロッチは相手のお腹の膨らみに気がつきました。身重のメス猫に、クロッチは「親方のこころざし」を潔くゆずったのです。
 三日ぶりに雨が上がった5月のある日、足場の撤去作業も無事に終わり、親方は、最後の確認のため、ひとり現場に戻ってきました。
いつも弁当を食べていた空き地のど真ん中に、子どものイタズラなのか、手折られた枝が置かれています。まっ赤な実をつけたヤブイチゴの枝でした。ふと目を上げると、ブロック塀の上にあいつが座っているではありませんか。
三日ぶりに雨が上がった5月のある日、足場の撤去作業も無事に終わり、親方は、最後の確認のため、ひとり現場に戻ってきました。
いつも弁当を食べていた空き地のど真ん中に、子どものイタズラなのか、手折られた枝が置かれています。まっ赤な実をつけたヤブイチゴの枝でした。ふと目を上げると、ブロック塀の上にあいつが座っているではありませんか。
親方をじっと見てつめています。
「こころざし、確かに受け取った」
親方はヤブイチゴの枝をそっと拾い上げ、クロッチに向かって大きく振ったのでした。
「似たものどうし」 作:かりにゃん
 「やっぱ、あいつ親方にそっくりっすよ」。金髪を五分刈りにした新入りの軽口に「バカヤロー、猫といっしょにするな」とすごんではみたものの、鳶(とび)の親方はまんざらでもありませんでした。
「やっぱ、あいつ親方にそっくりっすよ」。金髪を五分刈りにした新入りの軽口に「バカヤロー、猫といっしょにするな」とすごんではみたものの、鳶(とび)の親方はまんざらでもありませんでした。ここんとこ、鼻タレのわるガキもガラのわるいドラ猫も姿を消しちまった。あんなヤツ、久しぶりだぜ……。
それは、とあるビルの改修工事をはじめて間もないころでした。身の丈よりはるかに長い資材を担いで、地上3階の高さの足場を行き来していた親方は、現場の隣にそびえる松の木の上でこちらを見上げる1匹の黒猫に気がついたのです。 黒猫はあくる日もそのあくる日も松の上から親方を見つめているのでした。
うららかな春の陽射しを浴び、大きく伸びをしたクロッチは、ゴロリと寝返りをうちました─「それにしても……オイラより高いところに登れる人間がいたなんて」。
クロッチの自慢は「いつでもどこでもどの猫よりも、一番高い場所に陣取ること」でした。ところが、あの松のてっぺんよりもはるかに高いところを歩いている人間たちがいたのです。中でもクロッチの目をくぎづけにしたのは、目つきの鋭い白髪頭の男でした。小柄でありながら、重そうな荷を担いで幅の狭い足場板の上をひょいひょいと移動する姿を、クロッチは尊敬と称賛のまなざしで追い続けていたのです。
昼になり、弁当を広げた親方は、積み上げた資材の陰からこちらをじっと見ている猫に気がつきました。あの黒猫です。目尻がぐいっと上がったワルそうな目。なんと強烈な目めぢから力でしょうか。「おまえ、なんで毎日オレのこと見てんだよ」─話しかけながら親方は、まだ口をつけていない焼きシャケをそのまま猫の足もとに投げてやったのです。
一瞬、ためらうようなそぶりを見せた後、すっと前に進み出た猫は親方の目の前でゆっくりとシャケをたいらげました。こびるでもない、人を恐れるでもない、堂々とした食べっぷりにいたく感心した親方は、毎日やってくるようになった猫のためにシャケ弁を買ってきては、切り身をそっくりそのままを与えるようになったのです。
 「のら猫」の誇りをもつクロッチは、「なるべく人間から食べ物はもらうまい」と努めていました。
でも、今回は例外中の例外です。なんといっても、自分より高いところに登れる鳶の親方からの「こころざし」なのですから。
「のら猫」の誇りをもつクロッチは、「なるべく人間から食べ物はもらうまい」と努めていました。
でも、今回は例外中の例外です。なんといっても、自分より高いところに登れる鳶の親方からの「こころざし」なのですから。改修工事もあますところ数日となったその日、「おう、クロ、おそかったな」と、親方は勢いよく焼きシャケを放りました。すると、どこに潜んでいたのか、茶と黒のベッコウ模様の猫が飛び出してきて、シャケに前脚をのばした黒猫に思いきりパンチをくらわせたのです。黒猫は、とっさに身を引き、かろうじて一撃をかわすとすさまじい形相で無作法ものをにらみました。が、突然きびすを返すと、なにごともなかったかのように去っていったのです。あくる日、姿を見せたのはベッコウ猫でした。親方にしてみれば、強引に割り込んできた新参者に、シャケの皮でさえめぐんでやる義理も筋合いもなかったのですが、どういう理由か自ら身を引いた黒猫の気持ちを重んじ、工事が終わるその日まで、ベッコウ猫にシャケを与えることにしたのです。
クロッチからとびきりのごちそうをせしめたのは気性の荒いチャックロというのら猫でした。いつものクロッチであれば、エサを横取りしようとするものなど許しはしなかったでしょう。しかし、パンチをかわしたその瞬間、クロッチは相手のお腹の膨らみに気がつきました。身重のメス猫に、クロッチは「親方のこころざし」を潔くゆずったのです。
 三日ぶりに雨が上がった5月のある日、足場の撤去作業も無事に終わり、親方は、最後の確認のため、ひとり現場に戻ってきました。
いつも弁当を食べていた空き地のど真ん中に、子どものイタズラなのか、手折られた枝が置かれています。まっ赤な実をつけたヤブイチゴの枝でした。ふと目を上げると、ブロック塀の上にあいつが座っているではありませんか。
三日ぶりに雨が上がった5月のある日、足場の撤去作業も無事に終わり、親方は、最後の確認のため、ひとり現場に戻ってきました。
いつも弁当を食べていた空き地のど真ん中に、子どものイタズラなのか、手折られた枝が置かれています。まっ赤な実をつけたヤブイチゴの枝でした。ふと目を上げると、ブロック塀の上にあいつが座っているではありませんか。親方をじっと見てつめています。
「こころざし、確かに受け取った」
親方はヤブイチゴの枝をそっと拾い上げ、クロッチに向かって大きく振ったのでした。